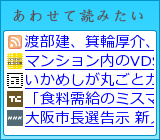つれづれっぽく読書雑記~気ままにブックレビュー
2010年10月に書いたページ。日ごろから雑多に読んでいる本・書籍について、読書感想文とか雑記とか、つれづれ気ままに書評・ブックレビューを記していきます。
2010年10月18日
「狙われたキツネ」ヘルタ・ミュラー
1989年12月、チャウシェスク政権が崩壊。
「狙われたキツネ 」は、革命前夜のルーマニアを描いた作品。
」は、革命前夜のルーマニアを描いた作品。
以前にも読んでいたが、ヘルタ・ミュラーが昨年、ノーベル文学賞を受賞したこともあり、新装版が発刊されたので再読。
ふたりの若い女性、教師のアディーナと工場で働くクララの姿を通して、独裁政権下の日常が描かれる。
上司に睨まれたアディーナは秘密警察の影に怯える。一方、クララの愛人は秘密警察の男。
ここでは誰もが猟師で、誰もがキツネになる。
栄養失調でイボだらけの指をした子どもたち。一方で独裁者は毎朝新品の服を着る。その不条理の世界では、絶望が風景まで変容させる。
大輪のダリアはキッチンや寝室を監視する。公園の空気にも恐怖がたちこめ、空はこの街を捨てて遥かな上空に出ていく。ひからびた日常を生きるうち、この国がドナウ川で遮られ、自分たちが見捨てられていることも当然と思えてくる。
不幸と絶望が、現実味いっぱいに描かれる。
独裁者は処刑されるけども、それすら「気にすることはない」。何も変わらないのだから。
この言葉に、独裁者が消えても、われわれ自身の中にも、その残酷さの種はあるのだと指摘されているように感じ、幸福とは、豊かさとは何かと考えずにはいられない。
「狙われたキツネ
以前にも読んでいたが、ヘルタ・ミュラーが昨年、ノーベル文学賞を受賞したこともあり、新装版が発刊されたので再読。
ふたりの若い女性、教師のアディーナと工場で働くクララの姿を通して、独裁政権下の日常が描かれる。
上司に睨まれたアディーナは秘密警察の影に怯える。一方、クララの愛人は秘密警察の男。
ここでは誰もが猟師で、誰もがキツネになる。
栄養失調でイボだらけの指をした子どもたち。一方で独裁者は毎朝新品の服を着る。その不条理の世界では、絶望が風景まで変容させる。
大輪のダリアはキッチンや寝室を監視する。公園の空気にも恐怖がたちこめ、空はこの街を捨てて遥かな上空に出ていく。ひからびた日常を生きるうち、この国がドナウ川で遮られ、自分たちが見捨てられていることも当然と思えてくる。
不幸と絶望が、現実味いっぱいに描かれる。
独裁者は処刑されるけども、それすら「気にすることはない」。何も変わらないのだから。
この言葉に、独裁者が消えても、われわれ自身の中にも、その残酷さの種はあるのだと指摘されているように感じ、幸福とは、豊かさとは何かと考えずにはいられない。
- プロフィール
- etacky エタッキー
- 地方在住者。
若干、活字中毒気味。
ただし読書速度は速くはないので、気ままに読み進めています。
- カテゴリー
- 最近のエントリー
 新着情報
新着情報
- Amazonサーチ
- 訪問者数
-
- 検索
- 最近のコメント
-
- 大分県中部を震源とする地震
- *Kuchenki opinie 01/14
- *peugeot 306 spalanie 02/15
- *voyage marrakech 02/21
- *fresh step cat litter 02/10
- *posicionamiento web mallorca 02/20
- *circuit maroc 02/21
- *phetteTriar 12/13
- *Cecille Bradstreet 01/25
- *Paulina Guay 01/26
- 大分県中部を震源とする地震
- 最近のトラックバック
-
- 「戦争を知るための平和学入門」高柳先男
- »cheap michael kors handbags [cheap michael kors handbags] 03/03 21:45
- »Chloe and Isabel reviews [Chloe and Isabel reviews] 03/03 15:23
- »louis vuitton handbags on sale [louis vuitton handbags on sale] 03/03 15:00
「MARI」八木啓代- »Read More Here [Read More Here] 03/03 20:06
- »Recommended Site [Recommended Site] 03/03 18:52
- »where can i buy it [where can i buy it] 02/17 16:42
「ぶらりあるき ミュンヘンの博物館」中村浩- »how to get a girl wet [how to get a girl wet] 03/03 20:02
- »executive chair [executive chair] 02/27 17:50
- »utility truck [utility truck] 02/27 01:55
- 「戦争を知るための平和学入門」高柳先男