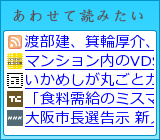つれづれっぽく読書雑記~気ままにブックレビュー
2006年06月07日に書いたページ。日ごろから雑多に読んでいる本・書籍について、読書感想文とか雑記とか、つれづれ気ままに書評・ブックレビューを記していきます。
« 2006年06月06日 | メイン | 2006年06月08日 »
2006年06月07日
「パナマの仕立屋」ジョン・ル・カレ
舞台は返還間近のパナマ運河。
利権の行方を巡り、各国の思惑が交錯する中、富豪や高官相手の仕立屋を営んでいるペンデルが“偽りの経歴を暴く”と脅され、英国のにわかスパイになってしまう。
監督官の追及に応じたいばかりに、ペンデルの嘘はふくらみ、遂には反政府勢力が蜂起するとのデマを創作してしまう。が、英国側がこれを真に受け、大々的な支援態勢に入ってしまい、事態は意想外の方向へ――。
揺れる英国大使館の様子に失笑しながら読み終えた。
スパイ小説と言えば、有能な登場人物が難事件を解決という形だったが、本書は、無能な人間が引き起こすコントロール不能な大事件を描く。
ある意味、冷戦後のスパイ小説の一つの道を示したと言えるかも知れない。
利権の行方を巡り、各国の思惑が交錯する中、富豪や高官相手の仕立屋を営んでいるペンデルが“偽りの経歴を暴く”と脅され、英国のにわかスパイになってしまう。
監督官の追及に応じたいばかりに、ペンデルの嘘はふくらみ、遂には反政府勢力が蜂起するとのデマを創作してしまう。が、英国側がこれを真に受け、大々的な支援態勢に入ってしまい、事態は意想外の方向へ――。
揺れる英国大使館の様子に失笑しながら読み終えた。
スパイ小説と言えば、有能な登場人物が難事件を解決という形だったが、本書は、無能な人間が引き起こすコントロール不能な大事件を描く。
ある意味、冷戦後のスパイ小説の一つの道を示したと言えるかも知れない。
- プロフィール
- etacky エタッキー
- 地方在住者。
若干、活字中毒気味。
ただし読書速度は速くはないので、気ままに読み進めています。
- カテゴリー
- 最近のエントリー
 新着情報
新着情報
- Amazonサーチ
- 訪問者数
-
- 検索
- 最近のコメント
-
- 大分県中部を震源とする地震
- *Kuchenki opinie 01/14
- *peugeot 306 spalanie 02/15
- *voyage marrakech 02/21
- *fresh step cat litter 02/10
- *posicionamiento web mallorca 02/20
- *circuit maroc 02/21
- *phetteTriar 12/13
- *Cecille Bradstreet 01/25
- *Paulina Guay 01/26
- 大分県中部を震源とする地震
- 最近のトラックバック
-
- 「戦争を知るための平和学入門」高柳先男
- »cheap michael kors handbags [cheap michael kors handbags] 03/03 21:45
- »Chloe and Isabel reviews [Chloe and Isabel reviews] 03/03 15:23
- »louis vuitton handbags on sale [louis vuitton handbags on sale] 03/03 15:00
「MARI」八木啓代- »Read More Here [Read More Here] 03/03 20:06
- »Recommended Site [Recommended Site] 03/03 18:52
- »where can i buy it [where can i buy it] 02/17 16:42
「ぶらりあるき ミュンヘンの博物館」中村浩- »how to get a girl wet [how to get a girl wet] 03/03 20:02
- »executive chair [executive chair] 02/27 17:50
- »utility truck [utility truck] 02/27 01:55
- 「戦争を知るための平和学入門」高柳先男